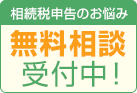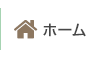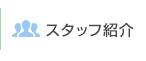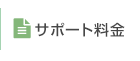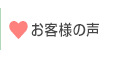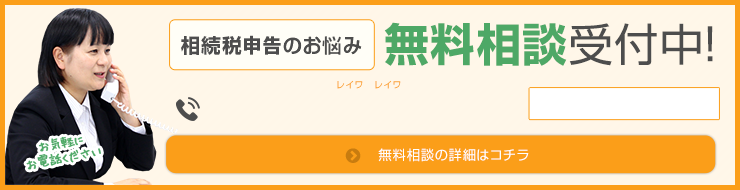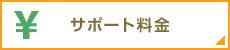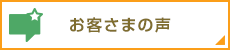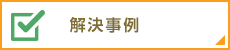注意!10ヶ月以内に相続税申告&遺産分割しなかった場合どうなるの?解決方法についても解説! | 遠州相続支援センター
相続が発生した際、相続税の申告期限は「被相続人が亡くなってから10ヶ月以内」と法律で定められています。この期限を過ぎてしまうと、さまざまな税務上の特典や控除が受けられなくなるリスクがあるため、注意が必要です。
特に大きなデメリットとしては、以下の3点が挙げられます。
①配偶者の税額軽減(配偶者控除)が適用できなくなる
②小規模宅地等の特例(居住用不動産の評価減)が受けられなくなる
③法定相続分に基づいて課税されるため、柔軟な遺産分割が難しくなる
これらは本来、相続税の負担を大幅に軽減できる重要な制度です。しかし、申告期限を過ぎると適用できなくなり、結果的に多額の税負担が発生する可能性があります。
この記事では、特に重要な「配偶者控除」と「小規模宅地等の特例」に焦点を当て、制度の概要と、期限内に申告しなかった場合の具体的な不利益について詳しく解説していきます。
目次
デメリット①:相続税の配偶者軽減(配偶者控除)が受けられなくなる

配偶者控除とは相続財産額の1億6000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額を控除できるという制度です。
この制度は相続税に関する控除の中でも活用されることがかなり多く、控除額も大きいです。
そのため配偶者控除があったから相続税が0円になったというケースも非常に多いです。
そのため相続税が発生しそうな方は早めに専門家に相談されることをおすすめします。
ただし配偶者控除は使わない方が良いケースもあります。
使い方や注意すべきケースについては下記よりご確認ください。
デメリット②:小規模宅地の特例(居宅特例)が受けられなくなる

居宅特例とは、配偶者や同居相続人が相続した場合には評価の80%を減額という特例です(最大適用面積330㎡)。
事業用宅地の特例は、相続人が事業継続した場合には評価の80%減額という特例です(最大適用面積400㎡)。
土地に関する制度は相続税を減額する際に非常に有効になりますので、こちらも対象の場合は絶対に使用したい制度になります。
居宅特例についても注意点や具体的にどれくらい節税されるのかをまとましたので下記よりご確認ください。
また、当センターにご相談いただきましたお客様で小規模宅地の特例を活用して実際に350万円節税したケースもあります。
実際に節税した事例について詳しくは下記よりご確認ください。
デメリット③:相続人全員が法定相続分で相続税を納めることになる

相続財産の全ての分配・相続が終わっていない場合「分割見込書」というものを作る必要があります。
分割見込書とは相続財産の分割が終わっていない理由と見込みを書く書類になります。
この書類があれば3年以内に遺産分割協議がまとまれば、相続税の還付申告は可能です。
しかし、まとまらなかった場合や忘れてしまうと法定相続分の相続税が発生しまうので注意が必要です。
デメリット④亡くなった方の預貯金の出金が制限され相続人の建て替えになる

相続が発生すると銀行口座などは制限されるため、家賃なども分散されるので、その納税は相続人の自腹になってしまいます。
民法改正により、未分割のままでも預金の一部は出金できるようになりましたが、全てではないので注意が必要です。
自身の場合はどうなのか知りたいという方は是非専門家への無料相談をご利用ください。
相続税の期限以外に気を付けるポイント!その他の期限は?

ここまでで相続が発生してから10ヶ月以内に相続税申告をしないとどのようなデメリットがあるのか解説しました。
相続税申告については相続が発生したらすぐに専門家の税理士にご相談されることをおすすめします。
また、相続に関して期限があるのは相続税申告の期限だけではありません。
相続には細かい制度と期限が沢山あります。
その他の相続手続きの期限は?
相続発生後にまず通夜や葬儀が行われますが、これらが終わると法律上の手続きや判断を行わなければなりません。
それぞれの手順にはの期限が定められており、期限を過ぎてしまうとペナルティが課せられることもあります。
ここではどのような手続きをいつまでに行わなう必要があるのかまとめます。
何をいつまでにやるか把握し、スムーズな相続手続きを行いましょう。
7日以内に行う手続と注意点
相続の発生をしってから7日以内に死亡診断書の取得、死亡届の提出、死体埋葬火葬許可証の取得を行う必要があります。
死亡診断書は病院で受け取り、死亡届は死亡した土地か本籍地の市区町村役場に提出します。
そして死体埋葬火葬許可証は上記と同じ市区町村役場で取得し、葬儀社に提出しましょう。
10日~14日以内に行う手続きと注意点
年金の受給停止の手続きも10日~14日で行う必要があります。
厚生年金であれば相続発生後10日以内、国民年金であれば14日以内に行います。
手続の際に戸籍謄本、年金証書、死亡診断書等が必要になりますので、事前に準備して社会保険事務所に提出しましょう。
3ヶ月以内に行う手続と注意点
遺言書の有無の確認も早めに行う必要があります。
遺言書がある場合はまず専門家へご相談いただくことをおすすめします。
また、法定相続人の確定も行う必要があります。
相続人の確定後、相続財産・債務の調査を行います。
相続財産・債務の状況次第で「相続放棄」または「限定承認」の意思表示を3ヶ月以内に
家庭裁判所に申述しなければなりません。
4ヶ月以内に行う手続きと注意点
所得税準確定申告をしなければなりません。
通常時において確定申告が必要な場合、翌年の3月15日までに前年分の所得の確定申告をします。
しかし、個人の死亡時においては、その年の1月1日から死亡日までの期間の所得を相続開始を知った翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。
10ヶ月以内に行う手続と注意点
相続財産・債務の確定・評価を行い、遺産分割協議をします。
ただし、相続人の中に未成年者がいる場合特別代理人を選任する必要があります。
遺産分割協議において、協議が成立した場合は遺産分割協議書を作成します。
協議が不成立の場合は調停、審判を行わなければなりません。
その後遺産分割協議書に沿って、相続人全員がそれぞれ取得した財産に対する相続税の申告・納税をしなければなりません。
相続税を現金納付するのではなく、その他の納税方法の延納・物納を選択する場合も10ヶ月以内に申告書を提出する必要があります。
1年以内に行わないといけない手続と注意点
遺留分の減殺請求をする必要があります。
遺留分とは、相続人が最低限引き継ぐことができる割合の相続財産です。
引き継いだ遺産がこの割合を下回った場合、他の相続人に減殺請求を行い、侵害されている遺留分を取り戻すことができます。
ただし、被相続人の配偶者または子のみが相続人として引き継ぐことができ、兄弟姉妹は対象になりません。
3年以内に行わないといけない手続と注意点
生命保険会社への請求があります。死亡保険は亡くなった翌日から3年以内に請求しなければなりません。
相続税についてご相談に来られる方の多くが、「相続税は資産家にかかるもので、自分には関係ないと思っていた」と仰られます。
確かに2016年1月の相続税法改正までは相続税が発生するのは殆どの場合資産家でした。
しかし相続税法の改正によってそれまでよりも相続税の納税対象者が大幅に増加しました。
これによって生前の相続税対策や、相続発生後の手続の重要性が高まりました。
申告期限に間に合わない!そんな時の対処法は?

もちろん、期限通りに申告ができるのが一番ですが、遺産分割協議が間に合わない、期日までに納税資金が確保できないなど、
どうしても間に合わない場合もあります。
そのような場合にはどうすれば良いのでしょうか?ここからは、どうしても間に合わない場合に取るべき対処法についてご紹介します。
①未分割のまま期限内に申告する
遺産分割協議が難航し、期限内に申告ができない場合には、未分割のまま申告を行いましょう。
正確には、法定相続分に従った内容で申告書を作成し、遺産分割協議がまとまったタイミングで修正申告を行うことができます。
これにより、罰則を受けることはなくなります。
ただし、未分割の申告では一部特例が使えなくなるので、3年以内に遺産分割を終えることが重要です。
②クレジットカードで納税する
相続税はクレジットカードで納税ができるため、納税のための現金が用意できない場合でも納税することが可能です。
一方で、手数料がかかることや上限金額の設定には注意が必要です。
③延納・物納
やむを得ない事情がある場合には延納や物納も認められています。
延納・物納については下記で詳しく解説しているので参照ください!
相続税申告期限ぎりぎりで申告をした事例

当センターには相続税申告に期限ぎりぎりで相談に来られる方もいらっしゃいます。
中には相続税申告の期限まで1ヶ月くらいの時期にぎりぎりで相談に来られて急いで申告手続きを済ませたというケースもあります。
10ヶ月以内の期限内に相続税申告を終えるためにはどうしたら良いか。
また、妹が母親と一緒に実家で暮らしていたため、妹は今後も実家に住めるようにしたい。というご相談でした。
こちらのご相談の解決事例は下記よりご覧ください。
また当センターにご相談いただくき相続税を350万円節税できた事例もございます。
相続税が発生しそうだが少なく出来ないか、自身が使える控除はないか知りたい方はまずは下記の解決事例をご覧ください。
相続の無料相談なら当センターの専門家にお任せください

当センターでは相続の無料相談を行っています。
相続のことなら何でも無料でご相談いただけます。
ご相談には相続の専門家税理士が親身に対応いたします。
袋井市、掛川市、磐田市を中心に静岡県全域のお客様のサポートさせていただいていますので是非お気軽にご相談ください。
ご予約は0120-0000-61よりよろしくお願いいたします。
無料相談の流れ
1.まずはお電話ください

税理士のスケジュールを確認し、ご相談の日時を調整させていただきます。
【電話受付】9:00~17:30
※土日や夜間の面談を希望の方は、調整いたしますのでご相談ください。
2.専門家による相談

無料相談では税理士がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただきます。
もちろん、相談内容に関しては、専門家の立場からしっかりとお答えさせていただきます。
3.サポート内容と料金の説明
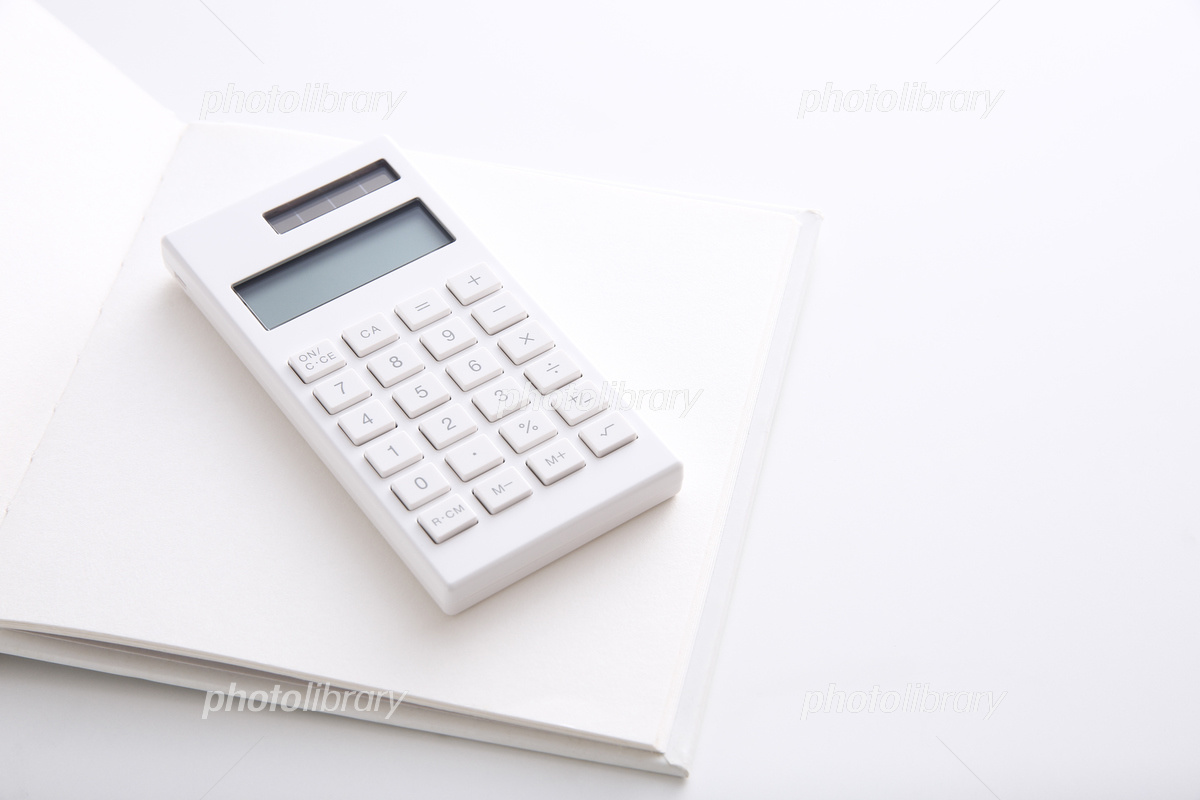 相続税の申告はもちろん!
相続税の申告はもちろん!
相続手続きに関する書類作成サポートなどは、前もってサポート内容と料金の説明を丁寧にさせていただきます。